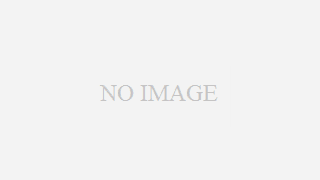 ギターモディファイ
ギターモディファイ 弦アース!
70年代中期〜後期にかけて製造されたギブソンのエレキギターはノイズが多いと思いませんか?これは、テイルピースやブリッジからポットまでの配線で弦アースが取れるというしくみになのですが、このころのギブソンはそれをしていません。そのかわりアースが...
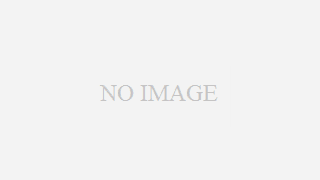 ギターモディファイ
ギターモディファイ 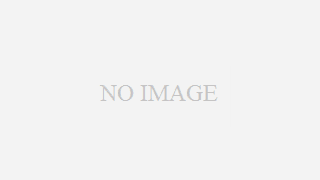 ギターモディファイ
ギターモディファイ 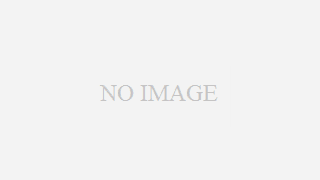 ギターモディファイ
ギターモディファイ 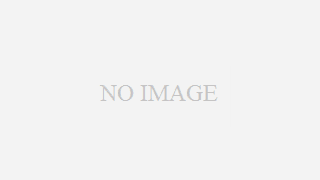 その他修理改造
その他修理改造 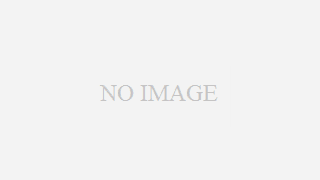 ギターモディファイ
ギターモディファイ 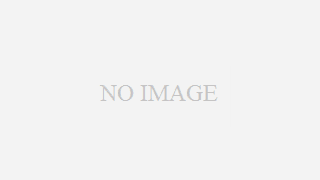 ギターモディファイ
ギターモディファイ 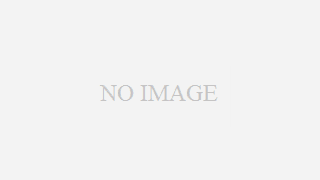 ギターモディファイ
ギターモディファイ 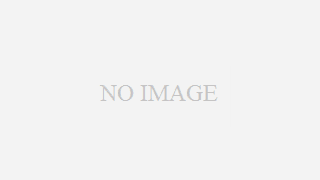 ギターモディファイ
ギターモディファイ 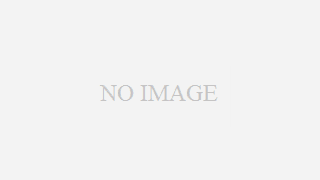 ギターモディファイ
ギターモディファイ 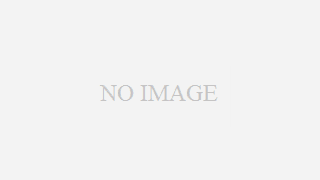 ギターモディファイ
ギターモディファイ